免疫理論に基づき、がんなどに関する健康相談を実施しています
 |
> がんと免疫 |
| トップページ | ご挨拶 | 瘀血とは | ブログ | 食養生 | がんと免疫 |
【免疫とは…】
免疫とは、私たちの体内に侵入した細菌やウィルスなどの外敵に対して働く、身体に生まれつき備わった生体防御(せいたいぼうぎょ)システムを免疫といいます。
その役割はおもに次の二つです。
1.外部から細菌やウイルスなどが体に入ってきた時には、免疫細胞がそれら「異物」と戦い、体を健康な状態に戻そうとします。
2.がん細胞など体の内部で生じる“身内の反乱者”を常に監視し、「異常」を見つけ出し、同時にそれらの動きを小さなうちに鎮圧して体の安定(恒常性=ホメオスタシス)を維持します。
言いかえれば、免疫とは、自分自身のものか(自己)、自分以外のものか(非自己=異物)を識別し、体をいつも健康な状態に保とうとしている自己防衛力と自然治癒力のことです。
免疫系の細胞(白血球系の細胞)は、まず骨髄(こつずい)の中で幹(かん)細胞がつくられ、成熟する間にそれぞれ特有の働きを持った細胞に分化し、免疫系という防衛システムを編成します。
分化した細胞には、リンパ球(T細胞、B細胞)、マクロファージ(単球が組織の中に入り、マクロファージに転換し細菌やウィルスを取り込みます)及び好中球(こうちゅうきゅう)・好酸球(こうさんきゅう)・好塩基球(こうえんききゅう)といった顆粒球(かりゅうきゅう)があります。
なおリンパ球幹細胞は胸腺(きょうせん)に移動すると、その中でT細胞になり、それはさらにT細胞(免疫系のアクセル役)、キラーT細胞(ウィルスなどの特定の抗原を直接攻撃する)、サプレッサーT細胞(免疫系のブレーキ役)などに分化します。
リンパ球幹細胞のうち、胸腺に移動しないものはB細胞になります。
ところで、免疫の防衛機構には二段階あります。
ひとつは常に体内をパトロールし、外敵を見つけると立ち向かって行く免疫細胞よりなる防衛システム(自然免疫系)です。
自然免疫系細胞には、マクロファージや好中球、NK細胞といったものがあります。
この常勤の防衛部隊では相手が屈強過ぎて防ぎきれない場合には、もうひとつの複雑でより強力な高度防衛システム(獲得免疫系)が働くことになります。
この免疫系はさらに液性免疫及び細胞性免疫の2つに分類されます。
免疫とは、私たちの体内に侵入した細菌やウィルスなどの外敵に対して働く、身体に生まれつき備わった生体防御(せいたいぼうぎょ)システムを免疫といいます。
その役割はおもに次の二つです。
1.外部から細菌やウイルスなどが体に入ってきた時には、免疫細胞がそれら「異物」と戦い、体を健康な状態に戻そうとします。
2.がん細胞など体の内部で生じる“身内の反乱者”を常に監視し、「異常」を見つけ出し、同時にそれらの動きを小さなうちに鎮圧して体の安定(恒常性=ホメオスタシス)を維持します。
言いかえれば、免疫とは、自分自身のものか(自己)、自分以外のものか(非自己=異物)を識別し、体をいつも健康な状態に保とうとしている自己防衛力と自然治癒力のことです。
免疫系の細胞(白血球系の細胞)は、まず骨髄(こつずい)の中で幹(かん)細胞がつくられ、成熟する間にそれぞれ特有の働きを持った細胞に分化し、免疫系という防衛システムを編成します。
分化した細胞には、リンパ球(T細胞、B細胞)、マクロファージ(単球が組織の中に入り、マクロファージに転換し細菌やウィルスを取り込みます)及び好中球(こうちゅうきゅう)・好酸球(こうさんきゅう)・好塩基球(こうえんききゅう)といった顆粒球(かりゅうきゅう)があります。
なおリンパ球幹細胞は胸腺(きょうせん)に移動すると、その中でT細胞になり、それはさらにT細胞(免疫系のアクセル役)、キラーT細胞(ウィルスなどの特定の抗原を直接攻撃する)、サプレッサーT細胞(免疫系のブレーキ役)などに分化します。
リンパ球幹細胞のうち、胸腺に移動しないものはB細胞になります。
ところで、免疫の防衛機構には二段階あります。
ひとつは常に体内をパトロールし、外敵を見つけると立ち向かって行く免疫細胞よりなる防衛システム(自然免疫系)です。
自然免疫系細胞には、マクロファージや好中球、NK細胞といったものがあります。
この常勤の防衛部隊では相手が屈強過ぎて防ぎきれない場合には、もうひとつの複雑でより強力な高度防衛システム(獲得免疫系)が働くことになります。
この免疫系はさらに液性免疫及び細胞性免疫の2つに分類されます。
【液性免疫】
抗体をつくって対応する:例えば細菌(抗原)が体内に侵入してきた時、T細胞とB細胞が協力して抗体をつくり、抗原に対応する免疫をいいます。
抗体がつくられる仕組みは次の通りです。
パトロール隊のマクロファージは抗原を取り込むだけでなく、 その抗原の情報を(高度防衛システムの)T細胞に伝えます。
T細胞はその情報をB細胞に伝え、抗体をつくるように司令します。
B細胞は司令どおり抗体をつくります。
抗体は免疫グロブリン(Ig)と呼ばれ、それにはIgG、IgM,、IgA、IgD、IgEなどの種類があります。
抗体が働くと、マクロファージは弱った抗原を取り込もうと再び駆けつけます。
抗体が1度つくられると相手を正確に判別する識別眼が残り、抗原が再び侵入してきた時には、それに対応する抗体が自発的につくられるようになります。
抗体をつくって対応する:例えば細菌(抗原)が体内に侵入してきた時、T細胞とB細胞が協力して抗体をつくり、抗原に対応する免疫をいいます。
抗体がつくられる仕組みは次の通りです。
パトロール隊のマクロファージは抗原を取り込むだけでなく、 その抗原の情報を(高度防衛システムの)T細胞に伝えます。
T細胞はその情報をB細胞に伝え、抗体をつくるように司令します。
B細胞は司令どおり抗体をつくります。
抗体は免疫グロブリン(Ig)と呼ばれ、それにはIgG、IgM,、IgA、IgD、IgEなどの種類があります。
抗体が働くと、マクロファージは弱った抗原を取り込もうと再び駆けつけます。
抗体が1度つくられると相手を正確に判別する識別眼が残り、抗原が再び侵入してきた時には、それに対応する抗体が自発的につくられるようになります。
【細胞性免疫】
がん細胞を丸ごと殺傷する;例えばウィルス(抗原)が体内に侵入し細胞をがん化させた時、キラーT細胞が“殺し屋”となり抗原に感染した細胞ごと殺傷する免疫をいいます。
ウィルスは体内に入ると、タンパク質の衣を脱ぎ捨てて、宿主となって私たちの遺伝子(DNAやRNA)に入り込み、そこにウィルス自体の成分を打ち込みます。
宿主の細胞が分裂するのに従い、ウィルスもどんどん増えることになります。
こんなことになっては大惨事です。そこで細胞性免疫が働きます。
この任務を担当するのが、T細胞から分化したキラーT細胞です。
キラーT細胞はがん細胞を丸ごと殺傷しようとします。
免疫には、自分の体の成分(自己)とは違う成分(非自己)を対象にするということ、すなわち「自己」とは決して反応しないという大原則があります。
その能力の厳密(げんみつ)さは徹底しています。なぜ、こうしたことが可能なのでしょうか?
答えは T細胞にあります。
胸腺内で自己と反応するT細胞はあらかじめアポトーシス(自壊死ーじかいし)という自死の方法で死滅し、取り除かれます。この結果、自分の免疫系は自分の成分を攻撃しなくなるのです。
がん細胞を丸ごと殺傷する;例えばウィルス(抗原)が体内に侵入し細胞をがん化させた時、キラーT細胞が“殺し屋”となり抗原に感染した細胞ごと殺傷する免疫をいいます。
ウィルスは体内に入ると、タンパク質の衣を脱ぎ捨てて、宿主となって私たちの遺伝子(DNAやRNA)に入り込み、そこにウィルス自体の成分を打ち込みます。
宿主の細胞が分裂するのに従い、ウィルスもどんどん増えることになります。
こんなことになっては大惨事です。そこで細胞性免疫が働きます。
この任務を担当するのが、T細胞から分化したキラーT細胞です。
キラーT細胞はがん細胞を丸ごと殺傷しようとします。
免疫には、自分の体の成分(自己)とは違う成分(非自己)を対象にするということ、すなわち「自己」とは決して反応しないという大原則があります。
その能力の厳密(げんみつ)さは徹底しています。なぜ、こうしたことが可能なのでしょうか?
答えは T細胞にあります。
胸腺内で自己と反応するT細胞はあらかじめアポトーシス(自壊死ーじかいし)という自死の方法で死滅し、取り除かれます。この結果、自分の免疫系は自分の成分を攻撃しなくなるのです。
【がんと免疫】
私たちの体の中では1日に数百から数千のがん細胞がつくられているということですが、免疫系はこれらのがん細胞を非自己の細胞として認識し攻撃を加えることになります。
がんの発生が多い年齢には、十歳前後と五十歳代の二つのピークがあります。十歳前後ではリンパ球の増殖・分化のスピードが最高潮です。
この増殖中のリンパ球が悪性化してしまうのがリンパ性白血病と悪性リンパ腫で、若年がんの殆どを占めています。
一方五十歳代には入ると、顆粒球優位の生体防御体制に移ります。
顆粒球は細菌を殺しますが,活性酸素もつくります。
高齢になるにつれ、特に細胞再生の多い部位に細胞の悪性化が起こり易くなります。
腸の上皮細胞は三日で置き換わると言われています。肺、乳腺、胃もまた細胞再生が激しい部位です。
それで大腸がん、肺がん、乳がん、胃がんなどが起こり易くなるのです。
がん状態では、がん抗原に対して免疫をつくるリンパ球「ヘルパーT細胞」の機能が障害され、応答性が低下することが大阪大学の研究陣によって明らかにされています。
この抗がん免疫抑制は、がんより生産されるTGF-β(腫瘍増殖因子ーしゅようぞうしょくいんし)によって起こされることが判ってきました。
恐ろしいことにがん自身にがんになった本人の免疫によって、がんを攻撃させない力があったのです。
またTGF-βは、抗がんサイトカインとなるTNF-α(腫瘍壊死因子ーしゅようえしいんし)、IFN-γ、IL-2、IL-4を全面的に抑制します。
また癌の進行に伴ってIL-6の生産が高まりますが,IL-6はTNF-αの産生を抑制します。
IL-2やIL-12は、TNF-γやINF-γを増強するものと推測されています。
がんは、がん細胞とがん患者本人の免疫力の戦いとも言えます。
免疫力を維持する(場合によっては高めて行く)ためには、効果的な食品成分(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)を毎日取ることも大事といえます。
私たちの体の中では1日に数百から数千のがん細胞がつくられているということですが、免疫系はこれらのがん細胞を非自己の細胞として認識し攻撃を加えることになります。
がんの発生が多い年齢には、十歳前後と五十歳代の二つのピークがあります。十歳前後ではリンパ球の増殖・分化のスピードが最高潮です。
この増殖中のリンパ球が悪性化してしまうのがリンパ性白血病と悪性リンパ腫で、若年がんの殆どを占めています。
一方五十歳代には入ると、顆粒球優位の生体防御体制に移ります。
顆粒球は細菌を殺しますが,活性酸素もつくります。
高齢になるにつれ、特に細胞再生の多い部位に細胞の悪性化が起こり易くなります。
腸の上皮細胞は三日で置き換わると言われています。肺、乳腺、胃もまた細胞再生が激しい部位です。
それで大腸がん、肺がん、乳がん、胃がんなどが起こり易くなるのです。
がん状態では、がん抗原に対して免疫をつくるリンパ球「ヘルパーT細胞」の機能が障害され、応答性が低下することが大阪大学の研究陣によって明らかにされています。
この抗がん免疫抑制は、がんより生産されるTGF-β(腫瘍増殖因子ーしゅようぞうしょくいんし)によって起こされることが判ってきました。
恐ろしいことにがん自身にがんになった本人の免疫によって、がんを攻撃させない力があったのです。
またTGF-βは、抗がんサイトカインとなるTNF-α(腫瘍壊死因子ーしゅようえしいんし)、IFN-γ、IL-2、IL-4を全面的に抑制します。
また癌の進行に伴ってIL-6の生産が高まりますが,IL-6はTNF-αの産生を抑制します。
IL-2やIL-12は、TNF-γやINF-γを増強するものと推測されています。
がんは、がん細胞とがん患者本人の免疫力の戦いとも言えます。
免疫力を維持する(場合によっては高めて行く)ためには、効果的な食品成分(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)を毎日取ることも大事といえます。


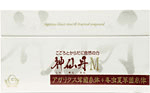
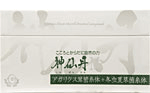
Copyright © 2005 Sinsendo All Rights Reserved.